谷崎潤一郎が、『 雁の寺・越前竹人形 』を褒めた、と書かれていた文章を読んだ。
ムスッとして、気難しそうな顔をし、文章にきびしい御大は、のちのノーベル文学賞を受賞した大江健三郎の文章の「てには」がおかしいと指摘した谷崎潤一郎が、『 雁の寺・越前竹人形 』を褒めた。
日本伝統の声が生きているとか、その当時の日本のふるめかしい声が聴こえてくる文章だと褒めたそうだ。
明治維新から昭和初期を題材にした小説のなかで、もっとも京都と若狭の言葉が再現されている小説のひとつだと思う。
はんなりとした、それでいてヌケメがなく、人を目踏みするような京ことばが、しっかりと書かれている。
幼少期の水上勉が、京都のお寺で修行したことと関係しているのだろうと思う。修行時代からお寺を飛びだし暮らした京都や幼少期にすごした若狭の風景や空気を水上勉が文章にそのまま落としこんでいる。
令和のいま消えはてたモノが文章にて描かれている。文章のなかには、いまもかわらずに屹立する二条城の櫓のように同じ光景を見出すこともできる。
『 雁の寺・越前竹人形 』を読むと、戦争につきすすむ時代の京都と竹と雪にかこわれている寒村の景色、そこに住まう人の息づかい、生きることの苦しみが、しかっと骨に刻みこまれる。
雁の寺・越前竹人形のどちらも悲話である。物語がはじまった瞬間から、悲しい結末になるしかない立場におかれ、翻弄され、椿の花のようにアッケなく落ちるか、猟銃で撃たれた鴈のように果てるしかない結末しか用意されていない。
あの時代には、石を投げれば悲話に当たったであろうことは容易に想像できる。たくさんの悲話があったのかもしれない。しかし、悲話はあまり伝わってはいない。
それは、なぜか、文章として残していないからだ。
水上勉が虚実をおりまぜつつ、当時の言葉づかいを忠実に再現した作品の舞台は、現実にあった悲話なのではと思わせる迫力がある。
そして、静かな竹林に誘いこまれるような、音のない白い世界にいざなわれるような魔性の力がある。
『 雁の寺 』は、水上勉の私小説のようにも感じられた。想像になるが、若い時分に、和尚様とお嫁さんの性行為をどこかで覗きみたのではと想像させられる。それぐらいに、性行為を覗きみた少年の心の機微がしっかりと書きこまれている。
悶々とした生活をおくり、反抗もできず、言いつけ通りに生きるしかない少年。
頭のなかでは、人を殺す計画をたてたとしてもなんら不思議ではない。その計画を実行しない人間が多勢をしめるだろう。
けれども、なにかキッカケがあれば、人間は殺人を犯してしまう。他人に犯されたがゆえに、殺人を犯してしまうかもしれない。
人間には、けっして犯してはならぬ領分があり、その領分をけっして穢してはならぬのだ。
その領分を犯し穢したときに雁は飛びさってしまう。
『 越前竹人形 』は、どこかで水上勉が越前竹人形を見て、物語を作ったと書いていたように思う。
悲しい結末をむかえるために、生きた二人の恋愛物語。いや、母子物語なのかもしれない。
母がおらず父ひとりに育てられた子。その子の身長は低く女性が苦手だった。その子は、父も女性が苦手だったと思っていた。
ところが、父には懇意にしていた女性がいたと知る。その瞬間にその子のなかにエディプス・コンプレックスが燃えあがる。また、マザーコンプレックスもかま首をもたげる。
女性も女性で、春を売っていた負い目、そして、母として見られるだけでなく女として見られたいと願う心境があった。
二人の歪な共同生活。ひとつの卑猥な毒薬がたらされる。ひとつの新たな命が、女性を苦しめる。
現在の我々では、想像もできない苦悩、田舎の閉塞感、封建的な社会の仕組みが、彼女を京都と福井の檻のなかにとじこめる。
そして、彼女は、川を紅く染める。
目頭が熱くなり、二人が幸せに暮らせた結末はなかったのかと考えこまずにはいられない物語。
竹は、どこまでも真っすぐに天にむかい伸びるが、世話をしないと折れてしまう。
筆をおくまえに『 雁の寺・越前竹人形 』は、どのような人に読んでもらいたい、もしくは読むべきか、を書くべきだろう。
20代に『 雁の寺・越前竹人形 』を読んだことがある。シンキクサイ物語だなとポイッと放り投げた。
20代からさらに20年すぎたいま、『 雁の寺・越前竹人形 』の一文字一文字がスッと体に浸透してくるようになった。
人生に酸いも甘いもしり、華やかなものよりもワビてサビたものに目にいくようになり、そして、すこし疲れた40代のかたに『 雁の寺・越前竹人形 』いかが。
水上勉のエッセイを読んだ感想も書いています。
水上勉の精進料理を再現し食べた感想を書いている記事です。


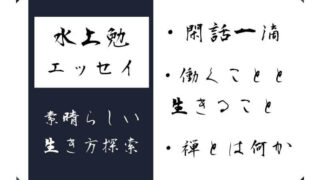

コメント